5日からの『いのちの食べかた』上映に際して、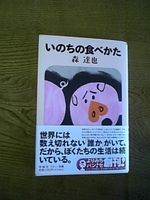
森達也著 理論社YA新書 『いのちの食べかた』という本を販売します。
これは、身近な出来事や題材についてさまざまな著名人たちが、噛み砕きながら尚かつきっちりと書き下ろしていく子どもたち向けのシリーズ、<よりみちパン!セ>の一冊です。
この『いのちの食べかた』はドキュメンタリー作家の森達也監督が担当しています。2004年に刊行されているのですが、その時は全く知りませんで、今回の上映に際して私は始めてこの本を手に取り読む事になるのですが、いやあ、面白いです。子ども向けということで、子どもたちに語りかけるように、そして非常にわかりやすい言葉で、想像力を手助けするように説明をしてくれます。
ここではお肉についてを中心に触れています。魚は丸ごと売っているけれど、お肉は丸ごとというわけにはいかない。そういえば、お魚が出荷される様子や市場の様子はTVなどでも映し出される事はあるけれど、お肉ははて、あっただろうか。それはなんでだろうか…。
私たちが目に見えているものは、例えばスーパーに並んでいるお肉のパックの姿で、次に考えていくとそれは豚だったり牛だったりという<動物>の姿がある。けれどその「あいだ」を私たちは知らない。想像はつくけれど、どこで、どんなふうに、どうやって、と細かく考えていくとわからない。そういった「あいだ」を知る事が大事なんじゃないかと、この本でも森監督は言います。
<そういえばそうだね>という<知っている事実>に囲まれて私たちは生活しているけれど、<そういえば、なんでそうなんだろうね>という事にまで踏み込まないでいる日常があることが、
するすると紐解かれていくようでした。
そしてそれは同時にさまざまな事にも言えるということもあらためて。
この本を読んでから再度映画を見返してみました。
見えなかった事が更に見えてくるという面白みを感じます。
映像が教えてくれる事、そして活字が教えてくれること…。
ドキュメンタリー映画の神髄にうちひしがれた。そんな気がしました。
映画と合わせて是非ご一読を、お勧めします。
===少なくとも、これだけは言える。何が大切で何がどうでもよいかの判断は、知ってから始めて出来る。知らなければその判断もできない。 森達也『いのちの食べかた』理論社===